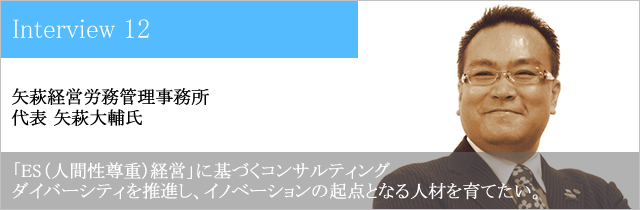
【profile】 矢萩大輔(やはぎだいすけ)
矢萩経営労務管理事務所 代表
社会保険労務士
有限会社人事・労務 代表取締役
一般社団法人日本ES開発協会 会長
903シティファーム推進協議会 会長
一般社団法人グリーン経営者フォーラム 代表幹事
JUNKANグローバル探求コミュニティ 会員
1995年に都内最年少の26歳で社労士人生をスタートし、
1998年、「ES組織づくりの有限会社人事・労務」を立ち上げる。
2004年に「日本の未来の“はたらく”を考える」を掲げ、CSR活動をスタート後、
一般社団法人日本ES開発協会(JES)を設立。
年一度、日光街道147kmを舞台に繰り広げるイベント「日光街道太陽のもとのてらこや」を主催している。
2011年に農園をスタート後、「下町の農と食で地域をつなぐ」を掲げる、903シティファーム推進協議会を立ち上げる。
2020年には、ボランタリーで運営する田心カフェをオープンし、農や食を通じて命のつながりを中心に置いた、地域社会やコミュニティづくりに取り組む。
2021年、ウェルビーイング×フィジカルを合言葉に「ウェルファイアカデミー」を開講。
身体性の伴った、幸福感ある起業を志す者が集う、web上でのメタバース環境を先取りしたMiroでのコミュニティの場を育てている。
ESを軸とした、いきいきとした職場づくりを目指して

今年開業27年目を迎えた矢萩経営労務管理事務所と併設する有限会社人事・労務にて、
人事制度や賃金制度設計等の組織開発及び、経営コンサルティングを中小企業向けに行っています。
弊社は、「人間性尊重経営」を掲げ、ES(Employee Satisfaction)を 土台とした企業の組織づくりにつながるサービスを提供しています。
企業が直面する問題の多様化、ビジネスモデルの変化、そして働く個々の価値観や抱える事情の多様化によって、
いわゆる「ピラミッド型組織」ではない、新たな組織のあり方が模索・実践されています。
このような従来の組織経営に変わって注目されているのが「コミュニティ経営」。
コミュニティ経営とは、一人ひとりの個性や考え方が尊重され、自由に働きながらも組織としてイノベーションを起こし続ける組織のあり方です。
こうした自律した働き方、持続的な経営を推進するため、他者(他社)や地域と協働しながら、これからのはたらくカタチを創造し、構築していくことが必要不可欠です。
私たち自身も多様なはたらくあり方・豊かさを探求するため、ソーシャルグッド推進プロジェクトに取り組んでいます。
「日本の未来の“はたらく”を考える」新しいはたらくカタチに触れ、学ぶ


「未来の新しい”はたらく力”を増やす」というテーマのもと、
勤労感謝の日がある11月に日光街道を舞台に開催する「日光街道 太陽のもとのてらこや」。
フィールドワークをまじえながら、みち、まち、ひとに学ぶ経験学習プログラムとして、
五日間に分けて日光街道147キロを歩き進みます。
日光街道沿いの各地域で暮らす、「越境するはたらき方の実践者」「つながりの基点として地域を動かすコミュニティリーダー」
「次世代の子どもたちへバトンをつなぐ立役者」「未来思考のはたらき方を自ら実践するロールモデル」に触れながら、
境をこえてつながりから価値を生み出す働くかたちを学ぶ場を創っています。
また、宿場町の一つ・春日部では、毎年グリーンフェスを開催。
日光街道沿いの地域をめぐる中でお世話になっている地域企業の方々に出店いただき、
地元高校生や大学生のサポートのもと、子どもたちに働く体験を提供し(はたらく体験ラボ)、地域ではたらくワクワクの根っこを育んでいます。
これからの社会において求められる、主体的な個が結び付き、つながりを基点としたこれからの働くあり方や、
自分自身の働く意味・役割を見出していけるような場を、仲間と共に創造していきたいと思います。
農は“はたらく”の原点。自律した多様な“はたらく”を体感する


地域のつながりの基点として、また「ガーデン・キッチン・テーブルをつなぐ」場として、
コミュニティカフェ「田心カフェ」を運営&自社農園である田心ファームにて、自然農法を実践しています。
生産から流通・販売まで一貫した“はたらく”を体感できる場を創っています。
人と人との関係、人と自然との関係、そして自然と自然との関係の中で、
自分自身が生きていく感覚を身に付け、暮らしに根付いたはたらくあり方、
お金に依存しない自律したはたらくあり方を実践を重ねながら、学んでいきたいと思います。
次世代の子どもたちのはたらく豊かさを!農と食を通じて地域をつなぐ


「下町の農と食で地域をつなぐ」をコンセプトに、地域の子どもたちの主体性を育み、
はたらく豊かさを体感してもらう場として、「よみがえれ!浅草田圃プロジェクト」を主催。
宮司さんの「地域のコミュニティの場になってもらえたらと」という想いが重なり、
台東区の秋葉神社さんにて、都市部の中で、子どもたちと“共に育てる”体験を提供しています。
また、“ハレノヒ”として、地域のお店や企業の方々と共に、年2回のマルシェを開催。
暮らしから生まれるはたらきを体感する中で、この地域に暮らすことの豊かさ、
そこから生まれるはたらくことの楽しさを体感してもらう場を創造しています。
実際に働いているスタッフさんの声:30代前半男性

私は大学卒業後2年間他社で勤務した後に入社し、
勤続10年になります。現在人事労務コンサルティング担当として働いておりますが、
実は入社前は社会保険労務士がどのような仕事をするのか良くわかっていませんでした。
最初は足を引っ張っていましたが、代表を含め手本となる人事労務の専門家が社内に多くいるので、
様々な事が勉強でき成長したという実感があります。顧問先様の想いに耳を傾け、
人事評価制度や賃金制度設計等の人事労務業務に携われる事は、
独立を視野に入れた方にとってもとても良い経験になると思います。
社会保険労務士事務所の仕事は机に向かってコツコツと行うイメージですが、
弊所は仕事をしながらも会話が多いので、一人で仕事をするというよりも、
コミュニケーションを取りながらみんなで助け合って仕事をする環境です。
また、グループの活動を通じて農業体験や地域の方と交流する機会もあります。
このように社会保険労務士の業務と直接関係ない活動に対し、
参加してみたい、一緒に楽しみたいと思える人にとっては、とても面白い職場だと思います。